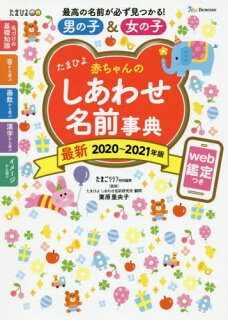植物の名前から
画数:7画
音読み:キョウ コウ ギョウ アン
名乗り読み:あんず
春に花を咲かせる杏の花から。品種や地域による差もありますが、杏が開花するのは概ね3月~4月の頃と言われています。
名前の例:杏奈(あんな)
2019年の明治安田生命の女の子の名前ランキングで、杏の表記が3位に、杏奈の表記が25位に入りました。
また、アンナの響きが43位に、アンの響きが50位に入りました。
4月1日 月曜日
おはようございます今日は 新元号 発表の日
千曲市「あんずの里」
(6年前 平成天皇皇后両陛下が
御訪問された場所)で
平成最後の
一目十万本と言われる
あんず(杏)の花が開花しました杏の花は 淡いピンク色
とても愛らしいです皆さま どうぞ
素敵な1日を…🌸#杏の花#開花 pic.twitter.com/i7afIC4Gte— itome🌸 (@itome0321) March 31, 2019
画数:10画
音読み:バイ 訓読み:うめ
名乗り読み:うめ、め
春に花を咲かせる梅の花から。品種や地域による差もありますが、桜が開花するのは概ね2月~3月の頃と言われています。
名前の例:彩梅(あやめ)

画数:13画
音読み:フウ、ホウ 訓読み:かえで
楓の字はもともとフウの木を意味します。
一説には、木と風を組み合わせた字。楓の種子が飛んでいく様を表しているのではないかとも。
春に花咲く楓の花から。
また、ハナノキのことを花楓(はなかえで)と呼ぶことがあります。花楓は春の季語とされています。
ややこしいことに、楓をフウと読んだ場合と、カエデと読んだ場合では植物が異なります。
フウは中国原産の落葉高木で、カエデは日本にも自生するカエデ科の落葉高木。
かつては、楓をフウ、槭をカエデと読んで区別していたようですが、槭が常用漢字ではないことから混同されるようになったようです。
なお、戦前は名前の表記に制限がなかったようですが、
戦後、1940年代後半ころに、法改正がなされたことで、人名に使える漢字に制限が設けられるようになりました。
楓は1981年に人名用漢字に追加されて、名前に使えるようになりましたが、槭は今のところ人名に使える漢字には入っていません。
もちろん、ペンネームなど本名でなければ使えます。
名前の例:楓(かえで)
2019年の明治安田生命の名前ランキングによると、楓の表記は女の子の名前で47位に入っています。
↓ハナカエデ
↓フウは緑色の花。
blogを更新しました。 Familiar flower in Sanda City Hyougo 三田市周辺の身近な花 : モミジバフウ(Liquidambar styraciflu https://t.co/zt7kg6ro7j pic.twitter.com/HjtgQM6HIH
— daiji_daiji (@daiji_daiji) 2018年4月21日
かのこ
鹿の子草(かのこそう)から。
春の終わりの頃に花を咲かせることから春の季語とされることがあります。
阿武隈川の下流散策…#カノコソウ(鹿の子草)
オミナエシの花によく似ているので「ハルノオミナエシ」とも・・ pic.twitter.com/1hrLq4K4l9— いまさき ひろし (@imasaki_hiroshi) May 3, 2017
かりん
春に花を咲かせる花梨から。カリンにはバラ科の花梨とマメ科の花梨があります。
バラ科の花梨は中国原産で、果実は花梨酒などに用いられます。マメ科の花梨は熱帯に自生し、木材に用いられます。
品種や地域による差もありますが、花梨が開花するのは概ね4月の頃と言われています。
名前の例:花梨(かりん)
↓バラ科の花梨
カリン(花梨)
別名 アンランジュ、モッカ(木瓜)、食わず梨
バラ科
花言葉「豊麗」「唯一の恋」「努力」 pic.twitter.com/f25cMWxuiP— こじやん (@koketilyann12) April 15, 2019
↓マメ科の花梨
[ASEAN Info] The Paduak (Pterocarpus Indicus). the national flower of Myanmar, blossoms in tin… http://t.co/SnQjNuMh pic.twitter.com/ZGyQsKiP
— ASEAN-Korea Centre (@akcsns) March 27, 2012
桜の画数:10画 櫻の画数:21画
音読み:オウ 訓読み:さくら
桜の旧字体は櫻。
春に花を咲かせる桜の花から。品種や地域による差もありますが、桜が開花するのは概ね3月~4月の頃と言われています。
また、春の襲(かさね)の色目。
桜月(さくらづき)とは、陰暦3月の異称。
名前の例:櫻子(さくらこ)
2019年、明治安田生命の女の子の名前ランキングで、サクラの響きが5位に、美桜の表記が23位に、桜の表記が32位に、桜子の表記が98位に入りました。
また、桜は女の子の名前に使用される漢字ランキングで14位。
さら
春に花を咲かせる沙羅(さら/しゃら)から。見頃は4月の頃。
仏教と縁の深い植物。沙羅双樹とは、釈尊が涅槃に入った時にその臥床の四方に2本ずつあったと言われることから。
インドの高地に自生する植物で、30mにも達するという大木。
日本では代用としてナツツバキが用いられることがありますが、沙羅双樹とナツツバキは全くの別物です。
沙羅双樹はフタバガキ科の植物、ナツツバキはツバキ科の植物です。日本で沙羅が見られるのは滋賀県の草津市立水生植物公園くらいなのだそうです。
2019年の明治安田生命の女の子の名前ランキングでは、サラの響きが22位に入っています。
左 夏椿 右 沙羅の樹(右側が仏教三大聖樹の一つ)
日本では温室でもなかなか育たないフタバガキ科の熱帯性植物。草津市立水生植物公園水の森で春に開花。 pic.twitter.com/Grynvug7f2— 寧楽Diary (@kougengigi) June 10, 2015
すずな
鈴菜(すずな)とは春の七草の一つ。青菜。カブ。
春の七草「せり、なずな、おぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」が入った七草粥を1月7日の朝に食べる風習があります。邪気を払い、万病を除くと言われます。
【菘 すずな】
春の七草のひとつ
鈴菜とも書く
蕪の葉の事を「すずな」とよぶ
カルシウムがほうれん草の5倍
カロテンはブロッコリーの3倍 pic.twitter.com/Rj7cuD3q3M— おかだけ@Japanese-food管理者 (@dile2oka8) January 5, 2020
画数:11画
音読み:キン、コン、ギン
名乗り読み:すみれ
春に花を咲かせる菫の花から。また、春の襲(かさね)の色目。
品種や地域による差もありますが、菫が開花するのは概ね3月~5月の頃と言われています。
2019年、明治安田生命の女の子の名前ランキングで、スミレの響きが48位に入りました。
名前の例:菫(すみれ)
〜菫
むらさきに菫の花はひらくなり人を思へば春はあけぼの
宮柊二花言葉:あなたのことで頭がいっぱい
自然はいつも優しい案内者ですね。
菫の花に春の訪れを感じた今朝。
#花 #菫 pic.twitter.com/adXvsScRtj— 風に徘徊(多忙・気まぐれ浮上) (@w_viburnum) February 23, 2015
宝塚歌劇を象徴するような“すみれの花咲くころ”も印象的です。
画数:7画
音読み:キン、ゴン 訓読み:せり
春の七草の一つで、春の季語。
春の七草「せり、なずな、おぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」が入った七草粥を1月7日の朝に食べる風習があります。邪気を払い、万病を除くと言われます。
一説には芹は草冠と斤(刃を近づける、刃物で刈る)を組み合わせた字。
名前の例:芹(せり)

画数:13画
音読み:チン
名乗り読み:つばき
椿はツバキを意味する字。
成り立ちについて、一説には、木+春(シュン)=ずっしりこもるで、幹の下方がずっしりと太い木という意味。
椿は春に花咲くことから春の季語とされることがあります。
娼婦マルグリット・ゴーティエと、青年アルマン・デュヴァルとの悲恋を描いた椿姫(つばきひめ)という小説/戯曲が有名。
名前の例:椿(つばき)

画数:8画
音読み:ダイ、ナイ、ナ
名乗り読み:なに
からなしを意味する字。
からなしとはリンゴとも花梨のこととも。リンゴの花も花梨の花も春に咲きます。
古代中国では奈はリンゴを意味すると言われています。
名前の例:環奈(かんな)
2019年、明治安田生命の女の子の名前ランキングで、杏奈の表記が25位に、紗奈の表記が43位に、優奈の表記が47位に、玲奈の表記が54位に入っています。
また、女の子にナがつく名前が大人気。響きのランキングでは、ハナが3位に、サナが14位に、ヒナタが17位に、ヒナが18位に、ユナが20位に、カンナが26位に、マナが31位に、ユイナが36位に、ユウナが38位に、ナナミとアンナとヒナノが43位に、エナとナナが50位に入っています。
奈は女の子の名前に使用される漢字ランキングで1位。
参考:奈は奈落の奈?
庭のリンゴの花…
ブランテル(リンゴの花ほころび〜♪で有名な「カチューシャ」の作曲者)の「リンゴの花咲く頃」という歌、思い出します。
若葉かおる五月の庭 リンゴの花咲き 流れてくる乙女たちの うたごえはたのし 君を待つひととき 幸にみつこころ 風そよぎ 花匂い 望みははるか〜♪ pic.twitter.com/EAmUgPsl2a
— 自由古書園「海つばめ」 (@oburo72) May 2, 2019
画数:11画
音読み:サイ 訓読み:な
からなしを意味する字。
菜とは葉や茎を食用とする草本類の総称、なっぱ、おかずを意味する漢字。
一説には草冠と采を組み合わせた字で、摘み菜(つみな)を意味すると言います。
漢字の意味から食べ物に困らないようにと名付ける人もいるようです。
また、菜の花は春の季語とされています。
鈴菜といえばカブ、花菜といえば花やつぼみを食べる野菜を指す(ブロッコリーやカリフラワー等)など組み合わせ次第ですぐに野菜や中華料理風になってしまうので組み合わせには注意が必要です。
名前の例:菜々子(ななこ)
2019年の明治安田生命の女の子の名前ランキングで、結菜の表記が15位に、陽菜の表記が18位に、愛菜の表記が36位に、陽菜乃の表記が43位に、菜月の表記が54位に、紗菜の表記が63位に、花菜の表記が98位に入っています。
また、女の子にナがつく名前が大人気。響きのランキングでは、ハナが3位に、サナが14位に、ヒナタが17位に、ヒナが18位に、ユナが20位に、カンナが26位に、マナが31位に、ユイナが36位に、ユウナが38位に、ナナミとアンナとヒナノが43位に、エナとナナが50位に入っています。
菜は女の子の名前に使用される漢字ランキングで3位。
春うらら☺️菜の花も満開です。お浸しにはまだなっていない(^^;;公園内には見えない風景。いや、富山県中央植物園内とは思えない風景。春ですなぁ〜♪
菜の花、アブラナ科アブラナ属因みにですが、野沢菜も菜の花の仲間でアブラナ科です。 pic.twitter.com/ELQdjSBGrt— hirosi h (@hirosanalps) March 16, 2017
画数:18画
音読み:トウ、ドウ
名乗り読み:かつら、つ、ひさ、ふじ
4~5月頃に花咲く藤の花から。また、春の襲(かさね)の名前。
名前の例:藤子(とうこ/ふじこ)

画数:10画
音読み:トウ 訓読み:もも
3月3日。桃の節句から。また、春の襲(かさね)の名前。
実際に桃の花が咲くのは、品種や地域による差もありますが、概ね3月下旬~4月の上旬の頃と言われています。
3月3日というのは旧暦での話で、月遅れといって実際に桃の花が咲く頃合いである、4月3日に桃の節句(雛祭り)を行う地域も存在しています。
着物と言えば季節先取りということがよくありますが、六日の菖蒲、十日の菊なんていう言葉も存在しているように、時機遅れはよくないけれど先取りはいいのでしょう。
名前の例:桃佳(ももか)
2019年、明治安田生命の女の子の名前ランキングで、モモカの響きが24位に入りました。
4月11日現在、桃の花開花状況🌸
昨日の雨にも負けず、まだまだ見頃が続いています‼️
菜の花はちょっぴり下向きですが…😢
この調子だと、今週土日まで持ちそうですよ✨
桃の色が濃くなってきて、とってもきれいです😊☀️ pic.twitter.com/93VmEbecmd— 山梨市観光協会 (@yamanashikanko) April 10, 2019
画数:19画
音読み:ラン 訓読み:あららぎ
名乗り読み:か
春に花を咲かせる春蘭(しゅんらん)から。品種や地域による差もありますが、春蘭が開花するのは概ね3月~4月の頃と言われています。
名前の例:蘭(らん)
シュンラン(春蘭) 別名:ホクロ(黒子)http://t.co/H4NiKgCPOeです。武蔵野の雑木林には思ったより多く残っている。自宅の近くで撮ったものです。#植物写真 pic.twitter.com/4wuSHfKaZw
— mnaeskeig (@Masegi_Ken) October 3, 2015
画数:11画
音読み:リ 訓読み:なし
春に花を咲かせる梨から。品種や地域による差もありますが、梨が開花するのは概ね4月の頃と言われています。
名前の例:梨花(りか)
「梨の花」
「県民の森」 近くの 矢板市長井は
りんご
ここ 大田原市湯津上は なし
サクラが終わるころに開花2018年4月21日 pic.twitter.com/0qD8uhFOkE
— masayuki1400 (@ms510723) April 21, 2018
るり
春に花を咲かせる瑠璃草(るりそう)から。
地域による差もありますが、瑠璃草が開花するのは概ね4月~5月の頃と言われています。
今日もお疲れさま
5月最初に撮ったのは
瑠璃草♪先日までこの辺に咲くはずって
感じで散歩してて。蕾もなかったのに
魔法のようにポンっと出てきたよ
(*´-`)#オールドレンズ倶楽部 pic.twitter.com/c34UYx6DXq— コニー (@u9lele1) May 1, 2019
れんげ
春の季語とされる蓮華草から。

参考:
明治安田生命(https://www.meijiyasuda.co.jp/enjoy/ranking/index.html)